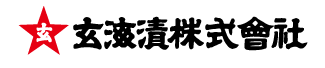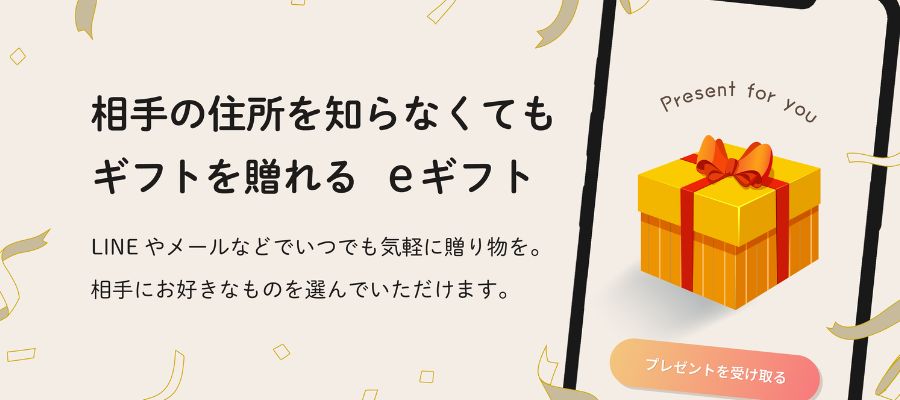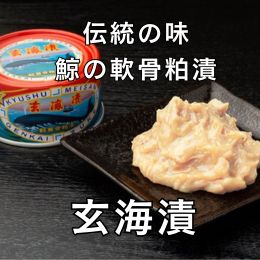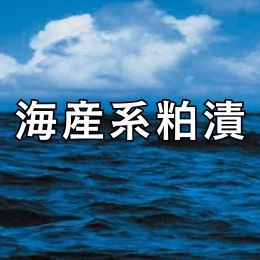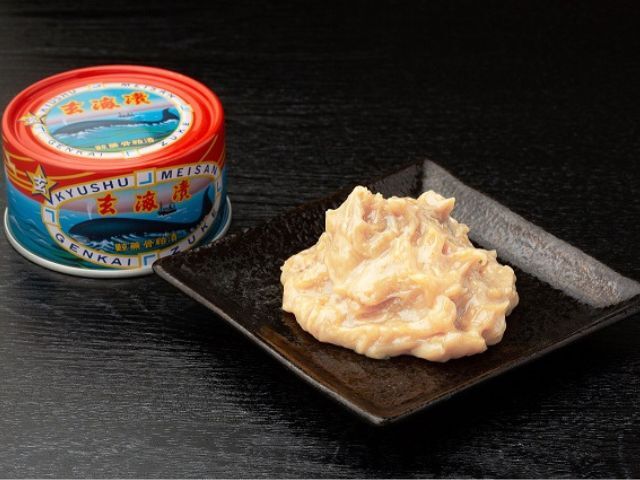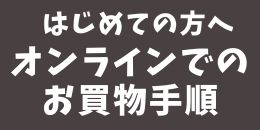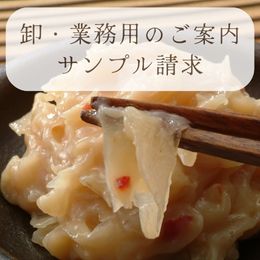商品カテゴリ
種類で選ぶ
贈る・ギフト
予算から選ぶ
用途で選ぶ
企画
玄海漬の人気ランキング!!
ちょっぴりおトク8%引き 高たんぱくで脂肪の少ないむね肉使用 ありたどりの大吟醸粕漬け(3枚入り)
¥1,200(税込)
高たんぱくで脂肪の少ないむね肉使用 ありたどりの大吟醸粕漬け
¥432(税込)
肥前さくらポークの大吟醸粕漬け3枚入り
¥1,500(税込)
肥前さくらポークの大吟醸粕漬
¥540(税込)
【次回使える200円券付】テレビ放映記念セット
¥4,980(税込)
玄海漬のオススメアイテム
【次回使える200円券付】テレビ放映記念セット
¥4,980(税込)
玄海漬(鯨軟骨粕漬け)K缶 160g
¥1,080(税込)
玄海漬(鯨軟骨粕漬け)袋入り 110g
¥648(税込)
玄海漬(鯨軟骨粕漬け)カップ入り 400g
¥2,592(税込)
【送料無料】 佐賀牛大吟醸粕漬け
¥5,500(税込)
添加物不使用 うりの粕漬
¥540(税込)
貝柱粕漬袋入り 100g
¥702(税込)
海茸粕漬け袋入り 100g
¥540(税込)
数の子粕漬袋入り 100g
¥540(税込)
野菜粕漬け 80g
¥324(税込)
かりかり(切干大根)粕漬け 100g
¥324(税込)
かりかり(切干大根)わさび漬 100g
¥324(税込)
蓮根粕漬 100g
¥324(税込)
クリームチーズの大吟醸粕漬け 60g
¥648(税込)
クリームチーズの西京漬 60g
¥648(税込)
柚子胡椒クリームチーズの大吟醸粕漬 60g
¥702(税込)
めんたいクリームチーズの大吟醸粕漬 60g
¥702(税込)
ドライフルーツ粕漬(りんご)袋入り
¥540(税込)
ドライフルーツ粕漬(パイン)袋入り
¥540(税込)
ドライフルーツ粕漬(キウイ)袋入り
¥540(税込)
珍味 酒粕ピーナッツ 90g
¥378(税込)
酒粕せんべい
¥324(税込)
珍味 おかか明太
¥540(税込)
茎わかめ粕漬袋入り 100g
¥324(税込)
かりかり雲丹 80g
¥540(税込)
カリカリチャンジャ漬 100g
¥400(税込)
玄海漬からのお知らせ
- 2026.2.4
博多大丸東館地下二階の催事コーナーにて玄海漬の試食販売を実施致します。期間は、2026年2月15日(日)~3月3日(火)まで!!
- 2026.1.6
1月4日(日)放送の「バナナマンの早起きせっかくグルメ!!」の朝限定の年始恒例特別プレゼント企画「せっかくほんのちょっと遅めのお年玉」 で玄海漬の「ありたどりの大吟醸粕漬け」が紹介していただきました。